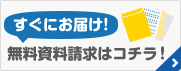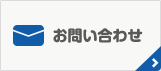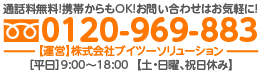自費出版を格安・高品質で!書店流通も可能な自費出版サービス
>良い文章の書き方
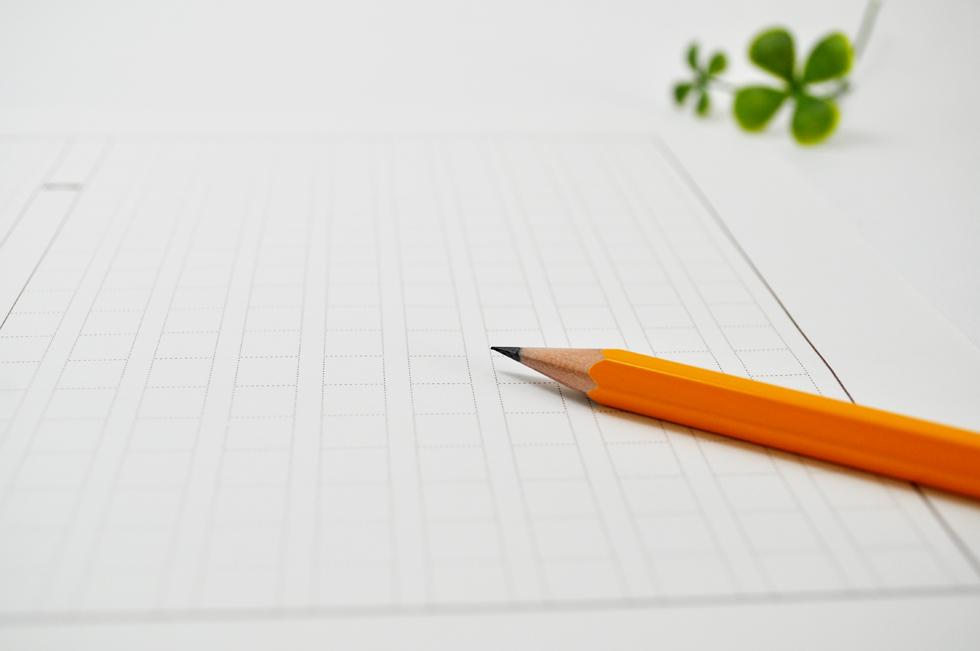
ここでは、お手軽出版ドットコムが長年の出版業務で培ってきた「良い文章の書き方」をお教えします。 文書には様々な表現方法があります。本の内容に応じた書き方で、読みやすい「良い文章」を目指すために、ぜひお客様の執筆活動の参考にしてください。他にも、文章の書き方や表現方法で悩まれた時は、お気軽にご相談ください。スタッフが丁寧にお教えいたします。
1基本的な文章作法
どのようなジャンルの文章を書く上でも重要となる、基本中の基本である文章作法を確認しましょう。 いわゆる、「作文のきまり」です。 学校で習ったけれど忘れてしまったという方も多いのではないでしょうか。
c段落の文頭は1文字分空ける
本文の始まりや段落の変わり目では、1番上を1文字分空けて書き出します。
c会話にはカギカッコを付け、改行して1番上のマスから書く
会話の部分は「 」をつけ、改行して1番上のマスから書きます。
cカギカッコでくくった文には、句点を打たない
カギカッコがあることで、1文の終わりと分かるので、 閉じカッコの前にも後にも句点を打つ必要はありません。 《×悪い例》 「昨日は、暖かくなりましたね」。 「昨日は、暖かくなりましたね。」 《○よい例》 「昨日は、暖かくなりましたね」 ただし、カギカッコの後に、新しい1文を続ける場合には、閉じカッコの後に句点を打ちます。また、カギカッコの後に、カギカッコの文が続くときは、その間の句点は不要です。 《×悪い例》 「昨日は、暖かくなりましたね」太郎は言った。 「昨日は、暖かくなりましたね」。「明日も暖かいでしょうね」 《○よい例》 「昨日は、暖かくなりましたね」。太郎は言った。 「昨日は、暖かくなりましたね」「明日も暖かいでしょうね」 ・行の1番上に、記号や句読点がこないようにする パソコンで文章を作成する際は自動で修正されるので意識していない方も多いのではないでしょうか。 句読点が行の最後のマスにきたときは、行末の文字の右下に打ち、次の行の初めにこないようにします。 「!」「?」などの記号も同様です。
c三点リーダとダッシュは2文字分使う
……(三点リーダー)や棒線(ダッシュ)は2字分のマスを使います。 長い沈黙などを表す時も、「…………」など、2文字×2回分使用し、必ず偶数となるようにします。 「………」など、奇数にならないようにしましょう。
c「!」と「?」の使い方
「!」や「?」の記号が出てきた後は、1文字分空けるようにしましょう。ただし、台詞の最後の場合でカッコを閉じる場合は、その必要はありません。 《例》 「おい!□気を付けろ!」 私は、赤信号に気付かずに渡ろうとした若者の肩を掴んで注意した。
c漢字や数字の統一
文章内で、同じ意味の複数の漢字を使ったり、漢数字と算用数字を混ぜたりしないようにしましょう。文章内での統一性がなくなり、読者の混乱を招きます。 《×悪い例》 「早く水漏れを直さないと。3日後にはお客様が来るのよ」 彼女の言う通り、三日後に親戚の集まりがある。昨夜の大雨で気付いた水洩れは、天井に大きなシミを作っていた。 《○よい例》 「早く水漏れを直さないと。三日後にはお客様が来るのよ」 彼女の言う通り、三日後に親戚の集まりがある。昨夜の大雨で気付いた水漏れは、天井に大きなシミを作っていた。 正しい例文の方は、「三日後」の部分が漢数字で統一されていますが、間違った例の方は、漢数字と算用数字が混じってしまっています。また、「漏れ」と「洩れ」の漢字も混同してしまっています。 このような間違いは、パソコンで変換する際には特に多いので気をつけましょう。
1文章作成の注意事項
基本的な文章作法の確認が終わったら、次は文章を書く際の注意事項を確認しましょう。 読者が読みやすいようになっているか、独りよがりなものになっていないか、注意してください。
c必要な句読点を正しく打つ
句点「。」は、文の終わりに打ちます。当たり前のことですが、意外に忘れる人が多いので注意しましょう。 読点「、」は、文を読みやすくし、誤解を防ぐために打つものです。 ただし、あまり多く打ち過ぎるのも禁物です。文章が細切れになり、読みづらくなるためです。 読点をつける原則としては次のような場合があげられます。 1、長めの主語を示した後 2、対等な関係の物事を並列する場合 3、原因と結果のあいだ 4、逆説と関係のあいだ 5、誤読を避けたい場合 《例1》 小さくて高価な宝石の警備が、厳重に敷かれている。 《例2》 緑は鮮やかで、川は澄み切っている。 《例3》 昨夜遅くまで起きていたため、今日は寝坊してしまった。 《例4》 桜が満開の季節なのに、雪が降るなんて異常気象だ。 《例5》 ①母親は、楽しそうにお絵かきをする娘を見ている。 ②母親は楽しそうに、お絵かきをする娘を見ている。
c余分な主語は省略する
主語を全く省略しない文章は、どこか不自然な感じを与えます。前文の主語と同じ主語を主語とする場合は、省略しても構いません。 ただし、前文と主語が変わる場合はきちんと明示するようにしましょう。 《例》 若者は、小さい頃から携帯電話に慣れ親しんでいる。携帯電話を持つことが普通なのだ。 ・主語と述語は、できるだけ近くに置く 主語と述語の間に、修飾語をたくさん入れると、意味の分かりにくい文になるので避けましょう。 《×悪い例》 当時、高校生だった私は、年に一度開催される吹奏楽部コンクールで、クラリネットを演奏した。 《○よい例》 年に一度開催される吹奏楽部コンクールで、当時、高校生だった私は、クラリネットを演奏した。 ・修飾語は、被修飾語の近くに置く 修飾語と被修飾語の関係を意識しましょう。 それぞれを出来るだけ近い位置に置いた方が、文章の意味が通じやすくなります。 《×悪い例》 決して私は、そのような悪い事はしていません。 《○よい例》 私は、決してそのような悪いことはしていません。
c長い修飾語は前に置く
長い修飾語と短い修飾語を並べるときは、長い修飾語を前に、短い修飾語を後ろに置きます。 短い修飾語と被修飾語との間に長い修飾語が入り込むと、読者は最初の短い修飾語のことを忘れてしまう恐れがあるからです。 短い修飾語はただでさえ印象が薄くなりがちですから、なるべく被修飾語の近くに置きましょう。また、そうすることで文章のリズムも良くなります。 《×悪い例》 凛々しい、まさに百獣の王と呼ぶにふさわしいライオンがいる。 《○よい例》 まさに百獣の王と呼ぶにふさわしい、凛々しいライオンがいる。
c「の」「が」「は」を繰り返さない
これらの言葉を繰り返して使用すると、文章が分かりにくく不自然になります。 ワープロソフトの校正機能を使うと、繰り返しが指摘されます。別の言葉に言い換えられないかを考えましょう。 《×悪い例》 名古屋の郊外の森の中のホテル 《○よい例》 名古屋市郊外にある森の中に建てられたホテル 同様に、「そして」「である」「だ」「思う」「かもしれない」なども、繰り返し使用すると単調な文章になってしまいます。 別の表現に直して、文章に変化を付けるようにしましょう。
c意味が重なる表現を避ける
意味が重なる「重複表現」を用いると、文章がしつこく、幼稚な印象を与えてしまいます。 言いたいことを丁寧に述べようとすると、重複表現になりやすいので注意しましょう。 《例》 犯罪を犯す→罪を犯す 電車に乗車する→電車に乗る いまだ未完成→いまだ完成しない 約1000人ほど→約1000人/1000人ほど 《例》 ×母親は、私が連絡するたびに仕事のことをいつも聞きたがる。 ○母親は、私が連絡するたびに仕事のことを聞きたがる。 ○母親は、私が連絡すると仕事のことをいつも聞きたがる。
c記号に頼りすぎない
(カッコ)、?、! などの記号は、多く使うと文章が稚拙になったり、大げさになったりします。 小説などの場合でも、地の文に「?」「!」などを使うと、大げさになってしまいます。文章の見出し、会話のセリフや引用など以外では、記号が不要な場合が多いです。 特に(カッコ)は、言い換え、例示や補足で使用している場合は言い換えができるので、なるべく(カッコ)を使わずに書いてみましょう。 《例》 ×この町には、公共施設(図書館や公園など)が多い。 ○この町には、図書館や公園などの公共施設が多い。
c正しい尊敬語、正しい謙譲語を使う
尊敬語と謙譲語の使い方を間違えると、相手に失礼なだけでなく、幼稚な文章になってしまいます。 また、「お召し上がりになられる」「お見えになられる」のように、二重敬語を使うと、かえって卑屈な印象になってしまうので注意しましょう。 《例》 単語:尊敬語(相手を上におく)⇔謙譲語(自分を下におく) 食べる:召し上がる⇔いただく 言う:おっしゃる⇔申す 聞く:お尋ねになる・お聞きになる⇔うかがう 来る:お越しになる・お見えになる⇔参る 行く:いらっしゃる⇔参る 会う:お会いになる⇔お目にかかる 会社:御社⇔弊社
c「ら抜き言葉」は文法的に誤り
最近では、「ら」を抜く「ら抜き言葉」を、「可能」の意味に使うことが多くあります。しかし、現段階では、書き言葉で「ら抜き言葉」は文法的には誤りです。 もちろん、小説での人物のセリフなどではこの限りではありませんので、自然な話し言葉として「ら抜き言葉」で書いても大丈夫です。ただ、地の文やビジネス書などでは、「ら抜き言葉」は使わない方が良いでしょう。 この他にも、「いまいち」「やっぱし」などのような、俗語や話し言葉は使わないようにしましょう。 《×悪い例》 食べれる・起きれる・見れる・来れる 《○よい例》 食べられる・起きられる・見られる・来られる
c「~など」の正しい使い方
例を表す場合に「~など」を使うときは、1つではなく2つ以上の例を挙げます。1つの例だけでは、全体のイメージがつかみにくいからです。 また、性質を表す場合に、「~などのように」と書く場合の「など」は省略できます。 《×悪い例》 イワシなどの魚が、たくさんいます。 チンパンジーなどのように、賢い動物。 《○よい例》 アジやイワシなどの魚が、たくさんいます。 チンパンジーのように、賢い動物。
c3つ以上の語句を並べる場合の注意点
3つ以上の語句を並べる場合、「と」「や」「および」などは、最後の語句の前に置きます。最後の語句以外は、読点で繋げます。 《×悪い例》 この夏休みに、遊園地と動物園、水族館に行きました。 甲および乙、丙は、~。 《○よい例》 この夏休みに、遊園地、動物園と水族館に行きました。 甲、乙および丙は、~。
c漢字と仮名の使い分け
文章をワープロで打つと、簡単に漢字変換ができます。しかし、あまり漢字を使いすぎると、重く硬い文章というイメージを与えてしまいます。 書いている文章の内容、対象とする読者層などを考え、漢字とひらがなを使い分けて、文章のイメージをやわらかくしてみましょう。 《例》 予め→あらかじめ、未だ→いまだ、余程→よほど 然し→しかし、即ち→すなわち、若しくは→もしくは ~程→~ほど、~毎→~ごと、~等→~など また、場合によって、漢字とひらがなを使い分けるべき言葉もあります。 「事⇔こと」「物⇔もの」「時⇔とき」「所⇔ところ」です。 基本的には、具体的に特定できる場合は漢字を使い、抽象的で漠然とする場合はひらがなを使います。 しかし、実際に書く場合は、前後の文脈から、漢字にすべきかひらがなにすべきか、読者の受ける印象を考えて使い分けるようにしましょう。
c大げさな言葉を多用しない
「とても」「非常に」「最高の」「最低の」「ものすごく」など、表現を大げさに見せる言葉は、使いすぎると読者は逆に冷めてしまいます。 強調したい言葉を具体的に説明するなど、誇張表現に頼らないで描写する方が良いでしょう。
c文章の中に過去形を入れる
文章は、現在のことは現在形で、過去のことは過去形で書きます。これを時制の一致と言いますが、日本語はこの時制の一致が厳密ではありません。あまり厳格に意識すると、かえって不自然な文章になります。 また、過去形と現在形を混ぜることで、文章に変化がつき、臨場感が出ます。 《×悪い例》 私は大学生の時、学園祭の実行委員会に入っていた。毎年秋に行われる大学祭の企画・運営を行うための集まりだ。11月中旬に2日間に渡って開催される学祭では、芸人やバンドなどを呼んで行われるステージ企画を始め、ゲームコーナーや模擬店など、様々な催しが行われた。4月には企画がスタートし、夏休みは準備に追われるなど1年を通して忙しいが、やりきった時の達成感は大きかった。特に引退の年には、感動のあまり、みんなで泣き出してしまうほどだった。 《○良い例》 私は大学生の時、学園祭の実行委員会に入っていた。毎年秋に行われる大学祭の企画・運営を行うための集まりだ。11月中旬に2日間に渡って開催される学祭では、芸人やバンドなどを呼んで行われるステージ企画を始め、ゲームコーナーや模擬店など、様々な催しが行われる。4月には企画がスタートし、夏休みは準備に追われるなど1年を通して忙しいが、やりきった時の達成感は大きい。特に引退の年には、感動のあまり、みんなで泣き出してしまうほどだった。
c適切な長さの文章にする
1つの文章があまり長く続くと、文章の構造が複雑になり、読者が理解しにくくなります。また、文法的な誤りも出やすくなります。 あまり長すぎる文章は、2つに分け、1つずつを短くする工夫をしましょう。 逆に、極端に短すぎる文章が連続すると、幼稚な印象の文章になります。 厳密に守る必要はありませんが、長い文章と短い文章を組み合わせて、平均の字数を30~40字ほどに揃えると読みやすくなるでしょう。
c表現を難しくし過ぎない
格調高くていねいな文章にしようと、漢語調や文語調の表現を多く使う人がいます。論文や試験ならばそれで構いませんが、あまり度が過ぎると、硬いイメージになり、読みにくく親しみにくい文章になってしまいます。 また、慣用表現や四字熟語も、たまに使用するのは文章を引き締めるのにとても有効ですが、こちらも多用し過ぎると同じような弊害があります。 特に、やさしいこと・簡単なことを難しい表現で表すことは避けましょう。 著者にとっては分かっていることでも、読者にとっては初めて見る分からないことばかりです。読者の立場に立って考えて、難しいことをやさしく伝えられるようにしましょう。
1文章推敲の注意事項
文章を書き終えたら、必ず確認をしましょう。 書き終わったときは完璧だと思っていても、後から見直してみると間違いが発見されるものです。
c推敲は時間をあけて行う。
自分の書いた文章を、書いた直後に見直してもおかしいところはないと思ったとしても、何日か経ってから読み直すと、変に感じることがあります。
文章を書き終えたら、数日おいて落ち着いてから、再度確認するようにしましょう。
c紙に印刷して確認する
現在は、パソコンで文章を書くことが多いと思います。パソコン上であれば、修正も簡単に行えるので便利です。 しかし、推敲する際は、パソコン上のままでは間違いに気づきにくくなります。パソコンの画面上の作業となるため、著者としての意識のままになるからです。 読者としての意識を持って作業をするためには、紙にプリントアウトして、視点を変えることが重要です。そうすることにより、第三者の視点で確認ができるため、画面上よりも間違いに気づきやすくなります。
c声に出して確認する
出来上がった文章を、実際に声に出して読んでみましょう。 音読することで、文章のリズムの良し悪しが分かります。読んでいて読みにくい部分は、文章のリズムが悪い部分なので修正すると良いでしょう。
c周りの人に協力してもらう
自分ひとりで間違いを全て見つけ出すのは、とても難しいです。自分で推敲の限界を感じたら、家族や友人など、周りの人に協力してもらいましょう。 自分では分かりやすいと思って書いた文章でも、他人から見たらわかりにくい表現になっているものもあります。率直な意見を求め、間違いや分かりにくい部分を指摘されたら、素直にしたがうようにしましょう。 また、ブイツーソリューションでは「簡易編集」「本格編集」として、オプションサービスで推敲を承っておりますので、ぜひご利用ください。
c推敲のチェックポイント
伝えたいことが読者にわかりやすく伝わっているか、文章が正しい日本語で書かれているか、確認しましょう。《代表的なチェックポイント》 ・誤字・脱字はないか ・慣用表現や熟語の誤用はないか ・句読点は正しく打ってあるか ・主語と述語はきちんと対応しているか ・文末の表現「である・だ」「です・ます」は混ざっていないか ・文末が単調になっていないか ・助詞や副詞は正しく使われているか ・接続語は正しく使われているか ・特別に意図する部分や会話文以外で、話し言葉を使っていないか ・一文は長すぎたり短すぎたりしないか ・文章のリズムが悪くなっていないか ・わかりにくい表現を使っていないか ・重複表現をしていないか ・しつこい表現(余分な修飾語や不要な繰り返しなど)はないか